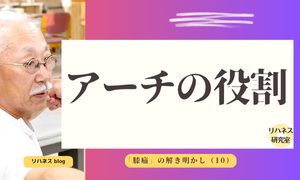 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし アーチの役割
しっかり「足指グリップ」することで、アーチ形成や下腿の傾き調整に役立ちます。そのアーチに役割は「体を支えるクッション」「衝撃を吸収する」「蹴り出しやジャンプなどのバネ」があげられます。膝の安定にとっても大切で、「足指グリップ」することで活性化します。
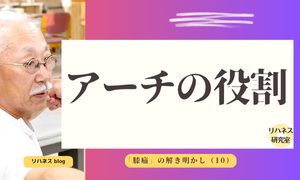 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 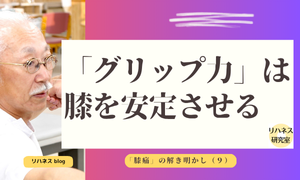 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 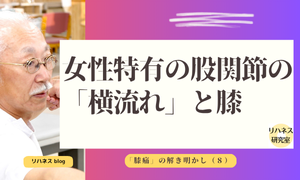 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 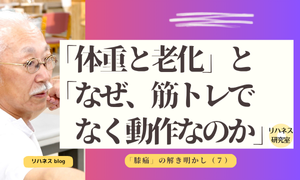 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 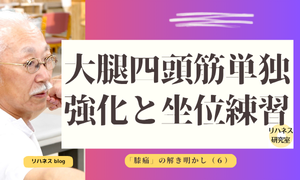 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 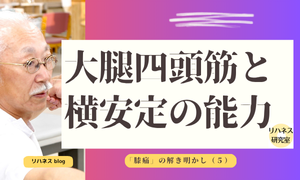 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 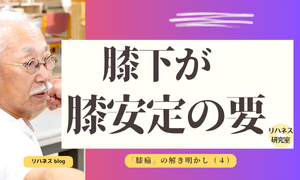 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 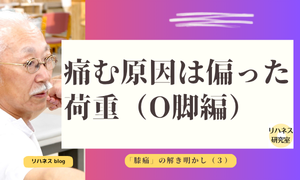 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 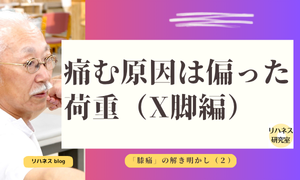 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし 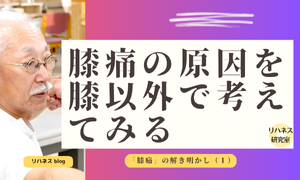 膝痛の解き明かし
膝痛の解き明かし