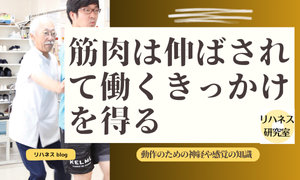 動作のための神経や感覚の知識
動作のための神経や感覚の知識 筋肉は、伸ばされて働くきっかけを得る
伸長反射は、筋肉内の筋紡錘からの伸長感覚情報からその筋肉の収縮を起こす現象です。反射は、定型的で融通の効かないと考えられてきましたが、近年は、反射には柔軟性があって、複雑な実際の運動に組み込まれているという考え方が支配的になっています。実際動作では、筋紡錘などの運動の結果情報がないとぎこちない動きになります。筋肉の出力調整は、感覚情報がないとが決められません。
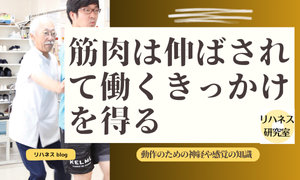 動作のための神経や感覚の知識
動作のための神経や感覚の知識 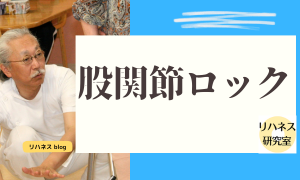 衰えの対策知識
衰えの対策知識 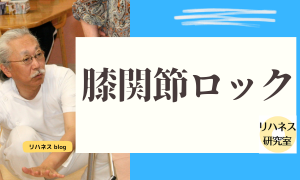 衰えの対策知識
衰えの対策知識 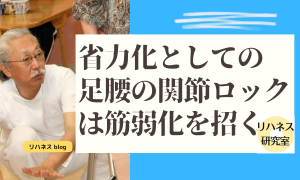 衰えの対策知識
衰えの対策知識 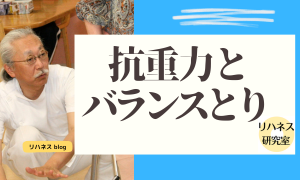 衰えの対策知識
衰えの対策知識