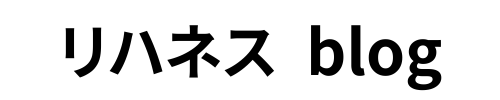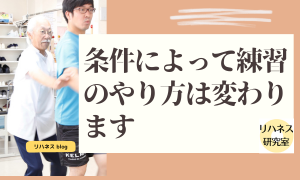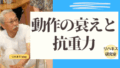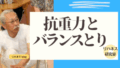動作練習では、今より動きやすくなること・痛みが軽くなることが大事なポイントです。
ただ、人はそれぞれ
性別・年齢・体型・柔軟性・筋力・体重・過去のケガや痛みなど、条件がみんな違います。
そのため、同じ練習でもやり方は人によって工夫する必要があります。
このページでは、動きを良くする練習をする上で知っておいてほしいポイントをまとめています。
性別と年齢
- 男性は中年以降、ホルモンの影響で急に筋力低下を感じやすい傾向があります。
- 女性はもともとの筋力が男性より低いため、O脚・X脚などになりやすく、痛みにつながることもあります。
- 筋トレは高齢でも効果がありますが、歳をとると筋肉が太くなりにくくなるため「筋肉の使い方」をより引き出す工夫が大切になります。
男性は、女性よりコミュニケーションが苦手の方が多いので家から出たがらず、活動低下が心配です。
柔軟性
- 体が硬い人:関節が動きにくいため、筋力に頼りがち → さらに体が硬くなる傾向
- 体が柔らかい人:柔らかさとバランスに頼って筋力を使わない傾向 → 筋肉が発達しにくい
若いうちはどちらでも大きな問題になりませんが、年齢とともにそれぞれの弱点が表に出てきます。
筋力や神経
- 筋肉量は30歳頃から徐々に減り始めます(80歳では10~30%減少)
- 筋力は50歳頃から下がりやすく、特に足の筋力の低下が早く、男性の方が急に落ちます
- 年齢とともに持久力(赤筋)に比べて、瞬発力(白筋)が衰えやすい変化があります
- 神経の切り替えも遅くなり、動きがスムーズにいかなくなることもあります
歳をとるにつれて「速い動き」「切り替えの速さ」「パワフルな動き」「しなやかな動き」などが苦手になってきます。
環境の変化
人間は、環境の変化に柔軟に対応できます。
使わないものを退けていく
・長期間のベッド臥床では、上肢より抗重力筋の方が筋肉萎縮が多かった。
適応するために自らを変える
・宇宙生活では、無重力環境で、抗重力筋の赤筋が少なくなり、白筋を増やす。
急な環境変化に合わせる時間は必要
・プールで泳いだ後、上がると体が重く感じる
・自転車を長く漕いだ後は、足が重く感じる
・宇宙飛行士の地球に帰還直後の抗重力筋の筋電図に乱れが確認されている
水中で動けたり、無重力で動けたり、人間(生物)の適応力はすごいです。その切り替え能力は年齢とともに低下するでしょう。
長く座っていて、体幹抗重力から急に立ち上がって、下肢の抗重力に切り替わる時にふらついたり膝痛を覚えたりすることもあるでしょう。
「力みタイプ」と「だらっとタイプ」、動作緊張の違い
動作緊張とは、聞きなれないと思います。当リハネス研究室でしか通用しません。
「動く時の力み具合の個人差」とでも言いましょうか。
動作を教える時に、人によって「力み具合」にかなり差があって、練習の仕方に影響があります。
・動作緊張の高い方「力みタイプ」
・動作緊張の低い方「だらっとタイプ」 に便宜的に分けています。
「力みタイプ」の方は、筋力優先・力が抜けずリラックスが苦手(椅子に腰掛けても面の支持でなくて点の支持傾向が強い。
一見姿勢良く見えますが、動きが硬いので、しなやかな動きはできません。硬さ故の腰や肩の問題など予想されます。
「だらっとタイプ」の方は、立っていても座っていてもヤジロベエ式に重さの吊り合わせや関節ロックを使って筋使用を省エネ化します。
一見「だらっと」した印象でしなやかですが、筋力の持続が苦手で「ゆるさ」故の腰や扁平足などの問題を抱えます。
両者とも、無意識でするので完全に治すことはできませんが、練習によって修正は可能です。
この発想は、脳卒中のリハビリ訓練で日常的に経験することです。
まとめ
人の動きは
性別・年齢・柔軟性・筋力・神経・環境・動き方のクセ など、さまざまな条件に影響されます。
そのため、誰にでも同じ練習方法が合うわけではありません。
あなたに合った方法を少しずつ取り入れながら、無理なく「動きを良くする練習」を行っていきましょう。